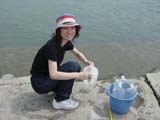多摩川ウイルス調査
はじめに
2003年4月〜2004年3月の1年間、多摩川の上流から下流までを対象とした腸管系ウイルスの調査を行いました。腸管系ウイルスは、食べ物や水を介して人の体内に侵入し、腸管細胞に感染して増殖します。ウイルスの増殖によって、下痢や発熱、嘔吐などの症状が発生します。ウイルスに感染した人の糞便中には非常に高い濃度でウイルスが排出されるため、下水処理場では適切なウイルスの除去、不活化が求められています。
下水処理場からウイルスを含んだ処理水が放流された場合、それらが水道水源として取水されることで水道水にウイルスに含まれる可能性があります。また、海や川でのレクリエーション行為でウイルスを含んだ水を誤飲してしまうことも考えられます。牡蠣などの貝類はウイルスを高濃度に蓄積することが知られており、未加熱あるいは加熱不十分でそれらを食することでウイルスに感染する危険性があります。
しかしながら、下水処理場からどのくらいの量のウイルスが環境中に放出されていて、川や海にどの程度の量のウイルスがいるのかについては十分に把握されていません。そこで、私の研究では、河川の流路全体を調査対象とすることにより、河川水がウイルスに汚染されていく実態の把握を試みました。
下の多摩川の地図の中に採水地点を示してあります。A〜Fの6地点で毎月1回の割合で河川水(表流水)の採水を行ました。A地点は奥多摩湖(東京都奥多摩町)、B地点は羽村取水堰(東京都羽村市)、C地点は多摩大橋(東京都昭島市)、D地点は稲城大橋(東京都府中市)、E地点は砧浄水場(東京都世田谷区)、F地点は二子橋(神奈川県川崎市)です。ご覧の通り、多摩川の中流域から下流域にかけては多数の下水処理場が見られ、河川が下水処理水に汚染されていると考えられます。
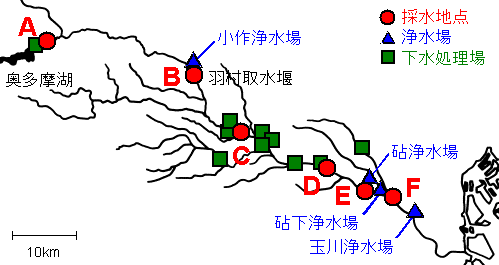
全12回の調査のすべてで中川技官に同行して頂きました。「走り屋」の異名に相応しいパワフルな走りで多摩川を駆け抜けて貰いました。黒田さんには計5回サンプリングを手伝って頂いた他、毎回の試料の分析にも協力して貰いました。また、片山講師、上條さん、チャネッターさんの3人には、1回ずつゲストとしてサンプリングに同行して頂きました。
写真をクリックすると拡大してご覧になれます。
また、写真にカーソルを合わせると説明を見ることができます。