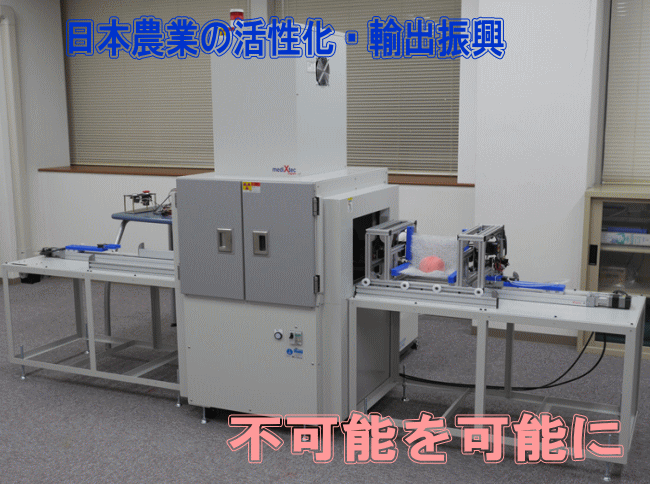
ニュース・更新情報
本研究グループは山梨県の呼びかけの「台湾向け輸出モモの選果に関する勉強会(平成22年10月27日)」の後、研究開発打合せ、情報交換会を随時行ってきた。
平成27年2月20日付にて、代表機関を山梨大学とし、山梨県・山梨県果樹試験場・サイエナジー株式会社が共同研究機関となり、農林水産業におけるロボット技術研究開発事業の研究グループとして設立した。
研究開発のポイント
研究開発の目的と課題
山梨県では台湾向けのモモ輸出の増大に努めている。しかし、台湾向けのモモ輸出においては、台湾の輸入検疫で、モモシンクイガの被害果が1個でも見つかると輸出がストップしてしまう。そのため、現在は人間による目視検査で検査しているが、目視では食入孔が小さいため100%の検出が困難であり、ルーペ等を用いた過酷な検査となっている。そこで、X線を利用して、果実内のモモシンクイガの幼虫を自動検出することで、果実収穫期の多忙な時期の農家に対する過酷な負担を軽減するとともに、台湾の検疫における不合格事例をゼロにすることができる。
研究開発の内容【概要】
複数方向からのモモ果実X線画像を処理し、自動的にモモシンクイガによるモモ被害果を検出するシステムを研究開発する。さらにモモを傷めずに移動・回転させるハンドリングロボットを研究開発する。
早期にプロトタイプ試作機を開発、評価し、実用化機の検討を行う。
研究開発の達成目標
1.100%の検出率
2.20%未満の誤検出率
3.1果実あたりの処理時間30秒以内
4.果実の品質保持100%
5.検出対象の幼虫のサイズの縮小化
研究開発の可能性や波及性
・パラメータを変更するだけで、多くの種類、様々な大きさのモモに対応することができる。
・パラメータを変更するだけで、モモに限らず、リンゴや梨にも対応することができる。
・全自動化のシステムなので、過酷な目視検査から解放され、より生産意欲が高まり、
高収入化に繋がる。
・収穫期の過酷な目視検査から解放される農業従事者は体力的にも非常に楽になる。